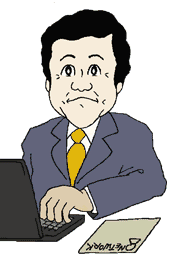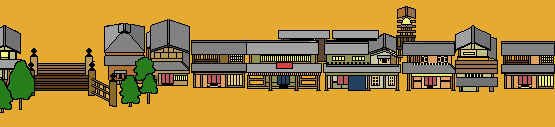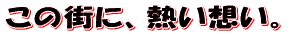
今、何故『リモデル』か
「リニューアル」(RENEWAL)の意味は<更新>で、店舗の改装の際などに使われて
います。
「リバイバル」(REVIVAL)とは、<再生>ですが、復古調のイメージが強くします。
「リフォーム」(REFORM)は本来、改良・改革という意味を持っていますが、流行遅れに
なった洋服の手直しとか、室内や家の改造の際に、使われる言葉となっています。
社会構造が土台から大きく変容している現在、今までの延長線上に、チョットした化粧
直しをする程度では成果が上がらず、「果実=利益」は実りません。
これまで培ってきた「資産」を、新しい時代のステージで、新しいコンセプトにより評価
し直して、あらゆる領域を巻き込んだ、総合的な「下町再生計画」を組み立てるべきでは
ないでしょうか。
改装でも、復古でも、手直しでもない・・・
「再生」⇒「REMODEL]⇒「リモデル」⇒「利も出る」
『利も出る計画』は、「再生」への提案
価値多元化の時代、先ずは一人ひとりにとって固有の大切な人、大切なもの、大切な
こと、即ち、個々の「宝」を明確にすることです。
「宝」を捉えることは、「それは何故(私の)宝なのか?」という、それぞれの<想い>を
集積することにつながります。
この「想い」の集積こそが、再生へ向けた最大の「宝」となり、「たから」を守り育てようと
いう意識が計画を推進するのです。
地域の活性化は「意思・意欲」をネットワーキングすることから始まります。
江戸/下町には『宝』が溢れている
改めて、下町の『宝』を明確にすることから始めてみましょう。
芸術・文化の、世界に向けた情報発信基地であり、木々の緑溢れる「上野公園」。
庶民の崇敬を集め、開基1300年を迎えた「浅草寺」。
そして下町文化文明の母なる川・隅田川・・・・・。これらが誰もが真っ先に上げる下町の
「宝」でしょうか。
もう一つ、「下町らしさ』という表現の中に、美味しい、楽しい・・・様々な「宝」が含まれて
います。
個々の<想い=宝>を具体化
最初のステップは、これらの「宝」を個々がイメージする色で表現することから始めて
みましょう。
暖色系・・・? 寒色系・・・? 赤ですか。白ですか。
それとも黒? 茶? 緑? 青?
次に、素材で表現すると、温もりのある「木」ですか、強靭な「鉄」ですか。
しなやかさもある「アルミ」ですか。透き通るように輝く「ガラス」でしょうか。
それとも「石」ですか。「レンガ」ですか・・・。
こうして、個々が「宝」を具体的に表していくことが第一歩です。
イメージした<想い=宝>が具体的になると、守ろうという意思と共に、育てようという
意欲が湧いてくるでしょう。
ここまで来れば、積極的にネットワーキングへと行動開始です。
「同志」の結集が街づくりの第一歩
「想いを集積」して、「宝」が具体的になってきたら、町が充実・発展をしていくための
材料が、以外に溢れていることに気づかれた筈です。
問題は基本方針を明確にして、この材料を、どのように組み合わせるかです。同時に
自助努力と協調性を発揮して、強靭な意志と意欲を持ち、<同志>を募っていくことです。
街づくりは、基本コンセプトを共有して、互いに努力していくことです。
他と同じことをしてはダメ!
旅に出て、駅に降りると、また駅前に立つと、どこも同じと一瞬思った経験は、どなた
にもあると思います。
折角、休暇をとって、憧れていた街へ来たのに、入口で○○○の街と同じという印象を
与えてしまったら、その時点で来街者の憧れは半減してしまいます。
よその繁華街に似た、どこにもあるような街を目指すのは止めて、徹底した<こだわり>を
持って、駅を降りた瞬間に「浅草に来たぞ!」「上野へ来たわ!」と、感じられる街づくりを
進めましょう。
昔の浅草は、日本最大の「テーマ・パーク」
庶民信仰の中心・浅草観音様と、下町の原風景を残した周辺界隈。大衆演劇、映画・・・。
様々な娯楽の発信基地であった六区興行街・・・。そして吉原・・・。
改めて、地図や文献を開かなくても、少し昔の浅草はディズニーランド以上に、テーマパーク的
な地域でした。
以上に・・・・・と敢えて云うのは、テーマ・パーク「昔の浅草」には、一番大切な<生活実感>、
即ち <生活の匂い>が魅力のひとつで、最も重要な構成要素となっていたことです。
素材を活かした、街づくり
数多くの<宝>を抱え、古くから栄えてきた街・浅草。
過去、いくつかの活性化プランや、再開発の構想が打ち上げられてきましたが、どれも
良い結果が出ていません。
それは、単なる一区画の再開発計画で、莫大な開発経費が見積もられ、経済的効果が
疑問視されるなど様々な理由が上げられています。
また、<想いの集積>が不十分なために、マクロ的な視野からの<コンセプト>が欠けて
いたことも影響しています。
先ず、基本的なコンセプトを構築
今、浅草の活性化策として、様々な議論や提案があります。
交通の便の良否を言う人がいます。馬券や車券等の売り場などギャンブル施設の拡張に、
賛否が云われます。
トレンディなディスコや、ライブハウスのオープンを求める声もあります。シネコンや劇場の
設置を求める声もあり、どれも大変貴重なご意見です。
でも、チョット待って下さい。どれも貴重なご意見ですが、現状を見て、一つ一つの良否を
議論する前に、この浅草をどうするのかという全体像と、そのための基本コンセプトを明確
にすることが先決です。
かっての浅草を思い描いて、懐かしみ、羨ましがって、現在の浅草にないものを求めて、
「あれはどうだ」「これはどうだ」と云って、膏薬を貼るように対処している時なのでしょうか。
出でよ! プランニング集団
冷静な歴史認識と、明快な現状分析を持って、客観的な将来展望と、愛と夢とロマンに
溢れた、総合的な「プランニング集団」の出現が、今こそ望まれているのです。
ここまで書いてきたら、思案を明確にして、多くの方の議論を仰ぎます。
『テーマパーク/下町構想』
ソフトウエアは<下町の心>
長い歴史と、年間数千万人もの参拝者数を誇る浅草寺。
日本を代表する祭・三社祭で有名な浅草神社。
この二つの寺社が、テーマパーク下町の中心ゾーンであって、ランドマーク・タワーと
いえます。
地元の人々は、観音様や三社様への崇敬の念を更に篤く(単なる宗教論議とは別)して
訪れる人々を気持ちよくお迎えする<たおやかな心>を持つことです。
たおやかな心⇒しなやかで、やさしい心の意
これこそが、「テーマパーク/下町」構想」のソフトウエアとも云うべき、基本戦略となるもの
です。
商うものは「温もり」「潤い」
日本は、物質至上主義の高度成長型社会から、西欧の国々のような<成熟型社会>に
既に突入しています。(社会資本の整備が、相当遅れていますが。)
このような時代認識に立つと、求められているのは利益・利潤を追求するためには、何で
もあり・・・の心がすさんだ社会ではない筈です。
大きく深呼吸して、周りの人々を気遣う心を再確認し、街を再発見し、自然や環境などに
心配りして、内面的な明るさ豊かさ、温もり、潤いを求めていく時代です。
当然、訪れる人が求めているのは、これらを満たした<やすらぎ>でしょう。
来街者には勿論のこと、地元の人同士も、お互いに<たおやかな心>で接することが
「テーマパーク下町」構想の原点です。
エリアを分けて「個性化」
次に地図を広げて、歴史・素材・環境・交通体系や人の導線など、考えられる様々な要素
を取り入れて、街を幾つかのエリアに分けてみましょう。
観音様の周辺は、浅草寺によって崇高な地域として、既に整備されています。
この観音様に詣でるための代表的な参道と言えば仲見世ですが、この他の参道整備など
各地域で充分議論を重ねて、エリアビジョンを創るべきです。
例えば、江戸の街並を再興したエリアや、文明開化の時代に徹したエリア、大正ロマン風
や昭和30年代などの街並、また近代的なエリアがあっても良いのではないでしょうか。
こうした街並でショッピングや食事を楽しむ・・・・・。エリアごとに雰囲気は違っても、映画・
演劇・音楽・・・・・発信される情報は、研ぎ澄まされたものであることは当然です。
路地、横丁を活かす
また「テーマパーク下町」で、もっとも大切にしたいのは、路地や横丁を活かす発想です。
江戸の街並を進んで、角を曲がると石畳がつづく大正ロマン風の横丁に出る・・・・・。格子
造りの路地から近代的な街並へ・・・。
大切なことは、職住近接/職住同居で、生活実感が漂ってくるようでなければ意味があり
ません。
バブル経済時代の発想である再開発型の街づくりではなく、「テーマパーク手法」を活かす
ことが必要で
軒先の草花や木までが、一生懸命生きていると感じられる整備が望まれます。
協調することが街づくり
今まで明確なコンセプトもなく、一貫性や、面としての地域景観への哲学も配慮も何もなく
個々がバラバラに自己主張をしてきました。
自己主張で許される範囲は、言論や個人の行動、着用する衣服や備品・・・・・で、嫌でも
他人の目に入る建築物や看板などは、もっと整合性を重視するべきではないでしょうか。
それぞれのお店が頑張ることは大切ですが、隣のビルは白色だから、自分のビルは緑の
タイルを貼りますでは、雑多な街しか出来ません。
デザインや素材、色などで下町を表現して、雰囲気という付加価値を付けてに売るのが、
テーマパーク下町の商いではないでしょうか。
一店舗のリニューアルと違って大変ですが、はじめは建物の色調や、看板・屋根の形の
統一などで協調すれば、基本コンセプトを表現していけるでしょう。
また、訪れた人々が歩きやすいように、自転車の置き方を工夫したり、歩道を塞ぐように
はみ出した看板を、少し引っ込めるような配慮をするなど、すぐに取り掛かれることは沢山
あります。
トータルコーディネイトが最重要
例えば、つくばエクスプレス浅草駅や、出入口のデザイン・色・素材などは、街に合わせて
トータル・コーディネイトされるべきです。
電車やバスを降りた瞬間、その街の雰囲気に、浸れるような街づくりが必要です。
そのエリアが<和風>を基調にしているのに、駅の出入り口が<洋風>だったら、訪れた
人々の期待は、半減してしまいます。
基本コンセプトが明快なら、郵便ポストは<赤>でなくてもいいのではないでしょうか。
個々が意見を開陳して、議論することは大切ですが、単にそれぞれの好みを言い合うの
ではなく、街路樹の種類も、歩道の素材や色も、公衆電話BOXや街灯のデザインも、乱雑
に置かれている飲料の自動販売機なども、全てトータルコーディネイトしていく、総合的な
プランニングと、実現するための協調が発揚です。
順序良く議論
ゴミ問題は・・・? 自由人対策は・・・? 各店の営業時間は・・・?
閉店後も街を明るくしてウインドウショッピング出来るように・・・? シャッターは・・・?
駐車場は・・・?公衆トイレは・・・? どうする!
こうして段階を追って、細やかな問題に入るのが順序でしょう。
この先は、皆様の議論を期待します。
このエリアには何々と提案するよりも、議論から始まります。
「下町再生」は、対症療法的な議論や懐古趣味や、一瞬に閃いた思い付きでは進み
ません。ましてや、他人への依存心を抱いたら尚更です。
長い景気の低迷もあって、営業的にも厳しい状況の中、一刻も早くよい結果を出したい
気持ちは、判りますが、でも基本コンセプトから始めなければならない時なのです。
それも街の人々がイニシアティブを取って、協力に進めることが大切名のです。
下町文化・文明は、庶民パワーが創りだす
街に人が溢れて、日々の商売が活気に満ちたものになることを願っています。でも、地元
の多くの本心は、新宿・歌舞伎町や渋谷のセンター街のようにとは、望んでいないでしょう
この土地で、日常生活が出来なくなるような街には、したくないというのが本音ではないで
しょうか。
職住近接、職住同居の街づくり・・・。こんな街づくりは夢でしょうか。
いや、夢ではありません。必ず出来ます。
昔から、俗に言う<御上>とは無縁の、エネルギッシュな<庶民パワー>で発展してきた
街です。
この街が大好きで、ここで商い、家族とともども生きていきたいと、皆、願っているのです
美味しいものが沢山あって、楽しいことが一杯あって、<たおやかな心>で迎えてくれる
街なら、人は必ず訪れてきます。
そんな日が、一日も早く来ることを願い、「テーマパーク/下町構想」が議論の端緒となれ
ば幸いです。
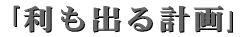

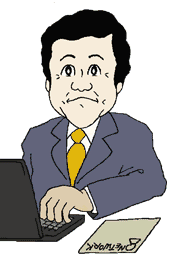
歴史・文化・伝統に培われた、私たちの台東区には、沢山の
「お宝」があります。
全国どこにもあるような町づくりではなく、「お宝」を活かして
『人が人として暮せる街、働く街』を創りたい・・・。
高度成長期のような再開発一辺倒ではなく、潤い/癒し・・・と
いう大事な要素に、もう少し目を向けて、成熟した街を創りたい
と願い、景観街づくり条例や色彩ガイドラインの制定などを提案
してきました。
こうした流れの中で、1996年の夏に記したのが、この「下町再生
利も出る計画」です。
その後、若干の加筆訂正を致しました。拙文ですが、ご一読いた
だければ幸いです。
再生⇒REMODEL⇒リモデル⇒利も出る
「下町再生/利も出る計画」 景観街づくり 編